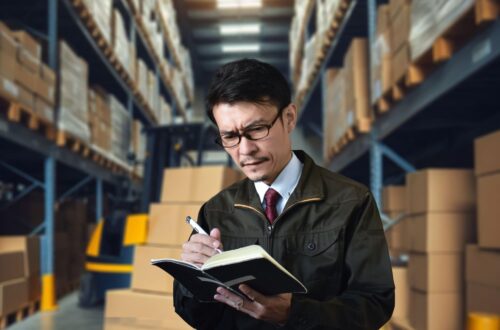企業の業務効率化が求められる今、特に改善の余地が大きいのが「受注処理」の分野です。多くの企業ではいまだに、FAXや紙の注文書を人が目で確認し、システムに手入力しています。こうした作業は時間と労力がかかるうえ、ヒューマンエラーの原因にもなりやすく、担当者の大きな負担となっています。
近年、この課題を解決する方法として注目されているのが、**RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とAI-OCR(人工知能による文字認識)**を組み合わせた仕組みです。AI-OCRが紙や画像の情報を読み取り、RPAがシステム登録や確認作業を自動で行うことで、これまで人手に頼っていた業務を効率的に処理できます。
本記事では、受注処理の現場で何が課題となっているのかを整理したうえで、RPAとAI-OCRがどのように業務を変えるのか、そして導入を成功させるためのポイントをわかりやすく解説します。「人の力×デジタルの力」で、受注業務をよりスマートにするためのヒントを見つけていきましょう。
受注処理の現場で起きている課題
多くの企業では、いまだにFAXや紙の注文書が日常的に使われています。
注文内容を目で確認し、システムへ手入力する作業は、担当者の経験に頼ることが多く、負担が大きいのが現実です。
また、ミスや転記漏れ、入力遅延が発生すると、納期や在庫に影響を与えるリスクもあります。ここでは、受注処理が抱える典型的な問題点を整理し、なぜ自動化が求められているのかを明確にしていきます。
紙やFAXによる受注対応が生む作業負担
現在でも多くの企業では、取引先から届く注文書をFAXや紙で受け取るケースが少なくありません。これらの書類は内容を一つひとつ確認し、販売管理システムなどに手入力する必要があります。日々の注文数が多い企業では、入力だけで何時間も費やすこともあり、担当者の負担は想像以上です。
しかも、フォーマットが取引先ごとに異なるため、同じ作業でもパターンを覚える手間が生じます。人が関与する時間が長くなるほど、集中力の低下による入力ミスのリスクも高まります。こうした手作業中心の運用では、生産性の向上に限界があり、人員を増やして対応するしかない状況に陥りやすいのが現実です。
人手不足が進む今、紙やFAXを前提とした受注対応を見直すことは、多くの企業にとって避けて通れない課題になっています。さらに、紙ベースの情報はデータ検索や共有が難しく、社内外の連携スピードを鈍らせる原因にもなっています。
ミスや入力遅延が引き起こす業務リスク
手作業で行う受注入力は、どうしてもヒューマンエラーを避けられません。数字の打ち間違いや商品コードの入力漏れなど、小さなミスでも納期や在庫に大きな影響を及ぼすことがあります。誤発注による返品や再出荷が発生すれば、余計なコストと手間がかかり、取引先の信頼を損なう原因にもなります。
また、繁忙期には処理が追いつかず、受注登録が遅れてしまうことも少なくありません。対応が後手に回ることで、在庫確認や出荷スケジュールの調整が遅れ、結果的に顧客満足度の低下を招きます。担当者が残業で対応するなど、一時的な努力で補う状況が続けば、職場全体のモチベーションにも悪影響を与えかねません。
業務の精度とスピードを両立するには、手作業中心の体制から脱却する仕組みづくりが必要です。さらに、こうしたリスクは企業全体の信頼性にも関わり、長期的には競争力低下を招く恐れもあります。
デジタル化が進まない背景と課題意識
受注業務のデジタル化が進まない理由の一つに、取引先とのやり取りの慣習があります。特に中小企業では「相手がFAXを使っているからこちらも合わせる」という事情が多く、システム化を進めたくても一方的には変えにくいのが実情です。
また、注文書の形式が取引先ごとに異なるため、自動化を導入しても正確に読み取れないケースがあります。さらに、IT投資に対するコスト負担への懸念や、社内での運用スキル不足も壁となっています。結果として、デジタル化の必要性を感じながらも、従来のやり方を続けざるを得ない企業が多いのです。
しかし、AI-OCRやRPAといった新しい技術を活用すれば、既存の帳票形式を維持したまま自動化を進めることが可能です。小さな改善から始めることが、現場の負担を減らし、将来的な業務改革へとつながります。加えて、社内の理解と教育を進めることで、デジタル化への抵抗感を和らげることも重要です。
RPA×AI-OCRで変わる受注処理の流れ
紙やFAXを使った業務を完全になくすのは難しいものの、その情報をデジタルデータとして取り込むことは可能です。AI-OCRが注文書を読み取り、RPAがシステム登録を自動で行うことで、これまでの手作業を大幅に減らせます。
実際に、導入企業では作業時間の削減や入力精度の向上といった成果が続々と報告されています。
この章では、どのように両技術が連携し、業務全体の流れを変えていくのかを解説します。
AI-OCRが帳票データを自動で読み取る仕組み
AI-OCRとは、人工知能を使って紙の文書や画像データに書かれた文字を自動で読み取り、テキスト化する技術です。従来のOCRでは印刷文字の認識が中心でしたが、AI-OCRではディープラーニングを活用することで、手書き文字や撮影した写真のような不鮮明な画像からでも高い精度で読み取ることができます。
これにより、FAXで送られてきた注文書や非定型のフォーマットでも、システムに登録できるデータに変換することが可能になりました。さらに、AI-OCRは帳票内のレイアウトを自動で解析し、「発注日」「商品名」「数量」などの項目を識別して抽出します。
人が目で確認して入力していた作業を短時間で処理できるため、現場の負担を大幅に軽減します。最近ではクラウド型のサービスも増えており、専門知識がなくても手軽に導入できる点も魅力です。こうした技術進化により、紙ベースの注文書が多い業種でもデジタル化の壁を越えやすくなっています。
RPAがシステム登録や転記作業を自動化
AI-OCRでデータ化された注文情報は、その後RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)によって自動的に処理されます。RPAは、人がパソコン上で行っていた定型的な操作をプログラムで再現する技術で、特定のルールに沿って作業を実行します。
例えば、読み取った注文データを販売管理システムや在庫管理ソフトに登録したり、確認メールを自動送信したりといった業務を休むことなく進めます。これにより、担当者が行っていた入力やチェックの手間が大幅に削減され、業務スピードが格段に上がります。
また、RPAは24時間稼働できるため、夜間や休日にも処理を継続できる点も強みです。人手では難しかった処理量のピーク対応も容易になり、安定した受注体制を維持できます。さらに、RPAの導入は他の業務システムとも連携できるため、受注から請求、出荷までの流れを一気に自動化することも可能です。
導入企業が得た成果と効果
RPAとAI-OCRを組み合わせた受注処理の自動化は、すでに多くの国内企業で成果を上げています。インフォマートの事例では、FAX注文書をAI-OCRで読み取り、RPAが自動入力する仕組みによって、処理時間を大幅に短縮しました。
これまで数時間かかっていた業務が数十分で完了し、担当者の残業削減にもつながっています。日立システムズの導入企業では、紙の伝票入力を自動化することで入力ミスがほぼゼロになり、顧客からの信頼も向上しました。
さらに、内田洋行が支援した食品業界の事例では、受注処理全体の工数を年間3,000時間以上削減する成果が得られています。このように、単に作業を効率化するだけでなく、人が付加価値の高い仕事に時間を使えるようになる点が大きなメリットです。AI-OCRとRPAの連携は、企業の働き方そのものを変える実践的なデジタル改革といえるでしょう。
導入を成功させるためのポイント
どんなに便利な仕組みでも、準備や設計が不十分だと期待した効果を得られません。特にAI-OCRやRPAの導入では、「どの帳票を対象にするか」「どの工程を自動化するか」といった検討が欠かせません。
また、完全自動化を目指すのではなく、人が確認する体制を残しておくことで、安定した運用が実現します。ここでは、失敗しない導入のために押さえておきたいポイントを具体的に紹介します。
帳票やデータの整理で認識制度を高める
AI-OCRを導入する際に重要なのが、まず帳票やデータの整理を行うことです。どれだけ精度の高いAIでも、入力するデータが複雑であったり、画像が不鮮明であったりすれば正確に読み取れません。特にFAXで送られてくる注文書は、印字のかすれや文字のズレなどが多く、誤認識の原因になります。
そのため、事前にスキャン環境を整え、明るさや解像度を一定に保つことが大切です。また、取引先ごとに異なる帳票形式をできるだけ統一し、レイアウトを簡略化することで、AIの学習精度が向上します。
さらに、過去の帳票データを分析して認識しにくい項目を洗い出し、ルール化することも有効です。こうした準備を丁寧に行えば、AI-OCRの精度は大きく改善し、手修正の手間も減少します。データの品質を高めることが、自動化全体の安定稼働につながる第一歩です。
人と自動化を組み合せた運用体制を作る
AI-OCRやRPAは非常に便利な技術ですが、すべてを機械に任せれば安心というわけではありません。システムが間違って認識したデータをそのまま処理してしまうと、誤った情報が取引先や社内システムに反映されるリスクがあります。
そのため、人による確認と自動処理をうまく組み合わせた運用体制を構築することが欠かせません。たとえば、AI-OCRが抽出したデータを一覧で表示し、担当者が一目で確認できる画面を設けると、精度とスピードを両立しやすくなります。
また、RPAが実行する工程の中に「承認フロー」を組み込み、最終判断を人が行う仕組みを整えることも有効です。完全な自動化を目指すのではなく、人が関与するポイントを残すことで、安定的かつ信頼性の高い運用が実現します。この“人×自動化”のバランスこそが、長期的な成功の鍵となります。
小規模導入から始めて継続的に改善する
AI-OCRやRPAの導入を成功させるには、最初から全社展開を狙わず、まずは小さな範囲で効果を確かめることが重要です。いきなり複雑な工程に適用すると、トラブルが起きた際に原因を特定しづらく、現場の混乱を招く恐れがあります。
最初は特定の帳票や部署に限定して試験的に導入し、実際の運用で得られたデータをもとに改善を重ねましょう。導入後は、AI-OCRの認識結果を定期的に分析し、精度の低い項目を学習データに追加することで、時間とともに正確性が高まります。
また、RPAのシナリオも定期的に見直し、業務の変化に合わせて最適化していくことが大切です。小さく始めて、運用を通じて育てていく――その積み重ねが、自動化を企業文化として根付かせる近道です。継続的な改善を前提に取り組むことで、長期的な成果を安定して得られます。
まとめ
RPAとAI-OCRを活用した受注処理の自動化は、単なる効率化ではなく、働き方そのものを変えるデジタル改革です。人が手作業で入力していた時間を減らし、確認や分析など付加価値の高い業務に集中できる環境をつくることができます。
また、AIの精度向上やRPAの拡張性により、従来は難しかった非定型帳票にも対応できるようになっています。これは、紙やFAXが残る業界にとっても現実的なDXの第一歩です。
導入を成功させるには、まず帳票やデータの整理を行い、人と自動化をうまく組み合わせた運用体制を整えることが欠かせません。最初から完璧を目指すのではなく、小さく導入して改善を重ねることで、着実に効果を積み上げていけます。
今後、労働人口の減少や業務の複雑化が進むなかで、こうした自動化の取り組みは、企業の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。RPA×AI-OCRの導入は、単なるコスト削減策ではなく、人がより創造的に働ける環境を実現するための投資といえます。